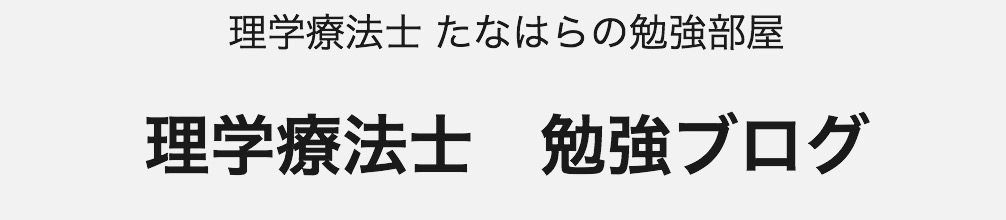本記事は、クリニカルリーズニングシリーズ4「治療手技総論」の9つ目の記事で、追加記事となっています。
本記事は、クリニカルリーズニングシリーズ4「治療手技総論」の9つ目の記事で、追加記事となっています。
臨床で、何かしらの治療手技を用いるうえで、手技そのものが持っているべき特性がいくつかあります。その中から以下の4つをピックアップして解説させて頂きます。
- 可逆的な変化を与える事ができる
- 反対の手技がある(リバーシブルな手技)
- 対応するセルフエクササイズがある
- 勘弁で、短時間ででき、即時効果を検証できる
1.可逆的な変化である事
ほとんどの徒手療法の手技は、その手技によって起こる変化が可逆的であるという事が言えると思います。
身体に何らかの変化を与えることができ、その変化は悪くなることも良くなることもありますが、それが可逆的な変化であるため、危険性を考慮した上で用いれば試験的治療を行う事ができます。
徒手療法に否定的な一部の治療家は、徒手療法の効果が、永遠に持続するものではない事をデメリットとして挙げ、「行う必要がない」と言う事もありますが、試しに用いた治療が、永遠に持続する可能性があるとしたら、これを用いる事はできなくなってしまいます。
こういった、可逆的な変化を引き起こす事ができる徒手療法を用いた介入は、経過をみながら判断することができ、後戻りすることができるというのが大きな特徴でメリットでもあります。
そして、徒手療法では、構造障害では説明のつかない現象に対しても対処することができるので、その適用可能性は非常に高いです。
手術という治療法を考えた場合、明らかな構造障害があって、これが症状の原因(症候性)であると判断できるまで、手術に踏み切れません。
しかし、「明らかな構造障害がない」もしくは「構造障害と症状が結びつかない」という場合でも、徒手療法による治療可能性というものは常に存在しています。
たった一回の治療で治すというよりは、適刺激を探した上で、場合によっては患者自身で、反復して刺激を繰り返すことで治療を進めていくことができます。
治すというよりは自然回復を促進させる(停滞させてしまっている回復メカニズムを促進させる)ため、もしくは、身体に備わっている疼痛抑制機構と呼ばれるものを促通するためにアプローチしている、という感覚が近いかもしれません。
しかし、これらの事も全て仮説にすぎないため、結局の所はアプローチしてみて、結果を見るまでは、それが有効な方法であるかの判断は不可能です。ですので、可逆的であるという事は非常に重要な部分となります。
2.反対の手技がある(リバーシブルな手技)
手術などの不可逆的な治療を行おうとした場合、それを試験的に用いる事は不可能です。「やってみてダメだったから、今度は別の方法にしよう」というような事が出来ません。
しかし、徒手療法の場合は、試験的に治療を行う事に何ら問題はありません。
徒手療法の全てではないが、リバーシブルな手技が存在する為、一過性に悪化させてしまったとしても、その反応から新たな仮説を生むことができます。
痛みを誘発するような、直接法に分類される手技を用いてみて、そのせいで悪化がみられたのなら、それをヒントに間接法を用いて治療をしてみるという、反対の選択肢をとる事ができます。
また、前回の治療強度を参考に、今日の治療強度を調整する事ができます。
もちろん、加えているテクニック自体を微調整する事もできます。例えば、筋膜リリースの方向が特定の位置から内方へ加えている場合、上内方に加えるのとどちらが、良い反応を示すかを確認する事もできます。
3.対応するセルフエクササイズがある
徒手療法は、身体に何らかの物理的刺激を加えて症状の変化を試みるものですが、その物理的刺激を理学療法士の手を用いずに行っても、同等の物理刺激を加える事ができれば、それは立派な治療法になります。
つまり、用い方さえ間違えなければ、セルフエクササイズと親和性の高い治療法です。
薬を用いた治療は、その薬がなくなると患者は疼痛の再発・増悪に不安をいだきます。
手術の場合は、再手術の可能性に怯えながら、ほとんどの患者が以前の生活スタイルには戻れなくなってしまいます。
医者からも「これからは無理をしないように」と言われ、仮に腰痛が再発した際は「また、無理はしていないですか?」と聞かれます。
一過性に出た痛みであって、以前の腰痛とは無関係だとしても、患者はこれを区別する事が難しく、それ以降の生活は狭められたものになってしまいます。
もちろん、全てが、そういう経過を辿るわけではないですが、私たちが治療に難渋するのは、そういった方々のはずです。
徒手療法では、効果を検証しながら、適刺激を見つけ、それに対応するセルフエクササイズ法を指導できれば、理学療法士による手を使用した治療をきっかけに、適切な自己治療法を発見でき、患者に必要以上の依存心を持たせてしまう事を防ぐ事ができます。
4.勘弁で、短時間ででき、即時効果を検証できる
用いる治療手技の効果判定が、その場でできるものである必要があります。
今、目の前の患者に適切な方法かどうかを確認する唯一の方法は、プレポストテストの結果です。エビデンスレベルの高さではありません。
そして、短時間ででき、即時効果を検証できるものにおいては、エビデンスは一切考慮に入れる必要はなくなります。必要なのはリスク管理のみです。難しく考えずに、まずやってみて、効果を検証すれば良いだけの場面で、必要以上の推論を行う事は「見えないリーズニングエラー」の1つです。
エビデンスが高いかどうかを確認する前に、実際にやってみて確認すればいいだけです。例えエビデンスが高くても、効果の有無を確認する必要があります。つまり、エビデンスの高さを確認する・しないに関わらず、この後の理学療法士の行動には影響を受けません。
ただし、この「一切のエビデンスを考慮する必要がない」というのは、短時間ででき、即時効果を検証できる場合においての話になります。
ですので、徒手療法を用いて治療に当たる際、実際に起きる現象をヒントにしながら、細かな調整を加えたり、リバーシブルな対応をしたり、繰り返し治療刺激を加えようとした場合、その効果のほどが、治療直後に現れる手技である必要があります。
検証するまでに1カ月の期間が必要な場合は、1カ月という長い期間を試験的に使う価値があるのかについて考えなければなりません。
患者の状態によっては、即時効果が出ない場合も考えられますが、そういった患者の場合は、今までの経験から、特定の症状パターン・運動検査結果から手技を選択していく事になります。(こういった患者像の治療選択については、今後記事にする予定です。)
患者の状態によってではなく、手技そのものの効果自体が1ヶ月後にしか現れない、という手技は基本的には選択する手技の中には最初から入りません。効果判定を行いやすいとする条件の患者で、何ら即時効果を見せてこなかった手技は、基本的には「手技を評価する過程」で淘汰され自身の引き出しから捨てる事になります。
また、「簡便」であった方が良いとする理由としては、再現性が1つに挙げられます。今後、繰り返し用いる可能性のある手技が、複雑すぎてしまい、同じように治療刺激を加えられないとなると困るからです。
そして、もう1つは、理学療法士が患者自身や患者家族に、「家族ができる対応手段」として、指導する事が可能となるからです。さき程挙げたのは、自動運動としてのセルフエクササイズでしたが、用いてきた治療の中には手を使用しなければ難しい物もあるはずです。
その方法に対応する自動運動がなければ、理学療法士が用いている実際の方法を患者や患者家族に提供すれば良いという事になります。
歩行が不安定な患者がいた場合、その家族に歩行介助の指導をしたり、起き上がれない患者がいた場合その家族に起き上がり動作の介助法を指導する事と同じ事です。
リハビリテーションの考え方では、周りの使える資源は全て有効に使うはずです。これは徒手療法を用いた痛み治療に対するリハビリテーションでも同様に考えるべきだと思います。
その際、実際に指導しようとした時に、理学療法士がも、何年かかけてやっと習得できるような特別な技術で治療に当たっている場合は、この点においてかなり不利です。
ですので、治療手技は、可能な限り、勘弁で、短時間でできる手技である事が望ましいと思います。
以下に、私が考えている手技が持っているべき特性・持っていると良い特性についてまとめました。上記で解説していない事も含まれていますが、記事の都合上割愛させて頂きます。
持っているべき特性
- 生体力学的変化を与えられる事
- 即効性があること ※目の前で変化の有無がわかる物理的刺激
- 危険性がないこと ※危険=症状を明らかに増悪させる可能性が高いもの、症状を増悪させる可能性が相対的に高いもの、症状の永続的な変化を与える可能性があるもの
- 短時間、長くても2分以内で終えられること
- 反復して行え、再現性があること
- 治療者、患者ともに負担がないこと
持っていると良い特性
- 体位のバリエーションがあること(効果判定を行う検査体位や症状が出る運動に近い体位で治療できること)
- 強度の調整が容易であること
- 誰にでもできる単純なものであること
- 同様の効果を出せるセルフエクササイズがあること
- もしくは、同様の効果を出せる自動運動があること
- 逆の効果を出せる対になる手技があること(リバーシブルな治療が可能)
- 患者の主観を聴取しやすい姿勢や状態であること
- 患者が手技の進行を理解しやすいこと ※機能的検査とセットになっていること
- 常識から大きく外れていないこと
- プレポストテストから対象患者を限定していけること
- 適・不適の判断が可能な検査が存在すること
ここで挙げた事は、全て実用性を考慮した上で必要となるものです。身体内で起きているメカニズムについての仮説が確立されていても、されていなくても、その手技の価値は変わらないと考えています。
最後まで読んで頂き、有難うございました。